胃液では炭水化物や脂質は分解されないのはなぜか?【物販奮闘記】
それぞれの臓器には役割が決まっています。例えば、「消化器」は、口から肛門までの器官です。つまり、「口」は消化器であって呼吸器ではありません。その口が呼吸期の役割=口呼吸がメインになっている人の体には、何が起きてしまうのでしょうか・・・。このような知識を分かりやすく説明できると、患者さまの納得度も変わります。今回は、消化器の一つである「胃」の役割について学んでいきましょう。
胃の役割

胃の役割といえば、「たんぱく質の分解」ということは理解されていますよね。では、なぜ胃でたんぱく質の分解をしなければいけないのか?それを考えたことはありますか?
嘔吐という行為を一度は経験したことがあると思います。嘔吐の原因は様々ですが、
「これ以上食べ物や飲み物を体に取り入れたくない」
「今は消化の活動をしている場合ではない」
「これは体内に入ってはいけないものだ」
など、とにかく「体の中に取り入れられたら困る」ときに起こるアクションです。
胃から先は十二指腸→小腸となり、吸収の工程に入っていくので、胃で吸収して良いものを選別するようなメカニズムができているのです。
空港では、手荷物を全てスキャンし、通ってはいけないものがないかをチェックしますよね?体の中でも同じことが起き要るのです。
胃は、体の中で、空港で言う保安検査場のような役割を持っているんですね。
では、皆さんに問題です。
胃液で炭水化物や脂質は分解されないのはなぜなのか?
胃液で炭水化物や脂質は分解されないのはなぜ?
それは、「たんぱく質を分解するペプシンが胃酸に含まれているからじゃないか?」と思う人が大半だと思いますし、間違いではありません。
重要なのは、たんぱく質と炭水化物・脂質との違いは何か?ということ。
食べ物をずっと放置していると、炭水化物や脂質は表面から傷んできます。正月にお餅を余らせて、表面にカビが生えてしまった!という経験をされた人もいますよね?それに対し、たんぱく質はどうでしょうか?
豚肉は「しっかり焼いてから食べないといけない」と昔、親から注意を受けたことがあります。中まで火を通すことで安全に食べられるのですが、なぜそう言われるのでしょうか?
それは、たんぱく質の腐食は表面だけでなく、内側にも侵食しやすいから。そして、菌は生きた状態で、表面だけではなく中側にも存在することが多いという理由。
胃酸(強酸)によって表面だけ消毒されても、内側には菌が残っている可能性があります。菌を弱らせたり倒したりするためには、たんぱく質を分解する必要があるのです。
だから、胃はたんぱく質を分解する消化酵素が出なくてはいけないのです。
体というものは、悪いものを吸収しないように工夫を凝らしているのです。
注目の記事
-
 就職活動のススメ【アトリクblog】
就職活動のススメ【アトリクblog】 -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム -
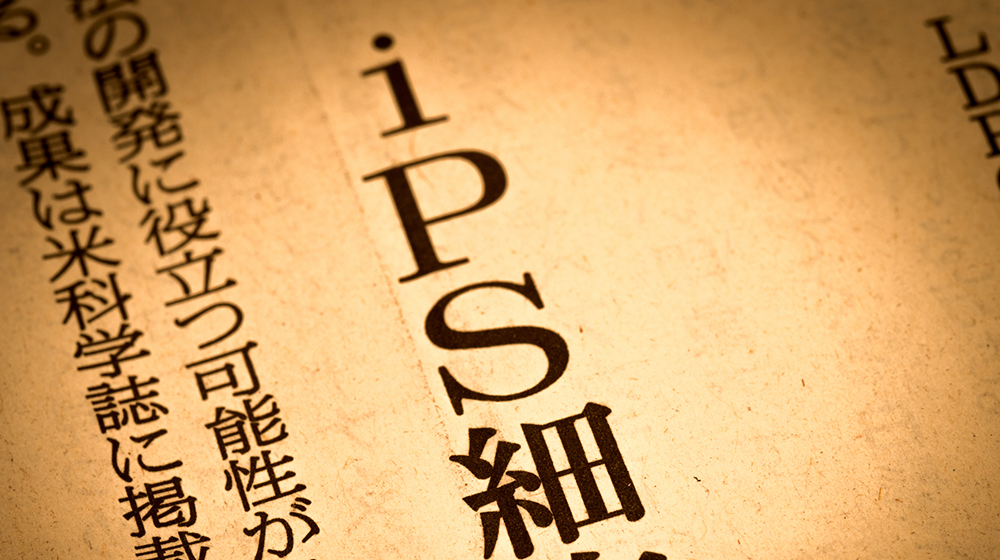 最先端医療連携
最先端医療連携 -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
 患者さまに伝えたい健康情報
患者さまに伝えたい健康情報 -
 患者さまに伝えたい健康情報
患者さまに伝えたい健康情報 -
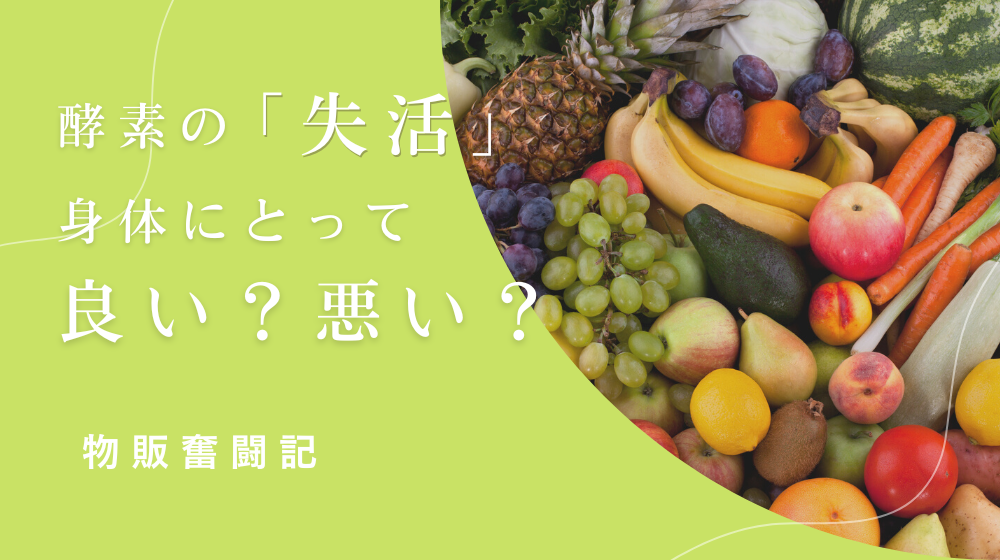 患者さまに伝えたい健康情報
患者さまに伝えたい健康情報
関連記事
-
 2022.06.27慢性痛には鎮痛薬が効かないのか関節痛や炎症の痛みを和らげるための手段として、患者さまが一番に思いつくのは、やはり「鎮痛薬」ではないでしょうか。すでに使用している患者さまもおられると思いますが、「市販の痛み止めを使っても効かない」という声もよく聞きます。痛みを抑えるはずの鎮痛薬が効かないのはなぜか。それは、痛みのメカニズムと鎮痛薬の作用機序に関係があります。
2022.06.27慢性痛には鎮痛薬が効かないのか関節痛や炎症の痛みを和らげるための手段として、患者さまが一番に思いつくのは、やはり「鎮痛薬」ではないでしょうか。すでに使用している患者さまもおられると思いますが、「市販の痛み止めを使っても効かない」という声もよく聞きます。痛みを抑えるはずの鎮痛薬が効かないのはなぜか。それは、痛みのメカニズムと鎮痛薬の作用機序に関係があります。 -
 2022.03.22導入10日目で22万円超?物販売上を急激に伸ばす「CBD」接骨院業界でも少しずつ広がりを見せている「CBD」。物販として導入し、初回の仕入れ分が10日間で全て売り切れた…という接骨院からの声が挙がっています。月間最高売上が140万円を超える院もあるほどです。接骨院でなぜここまでCBDの売上が伸びるのか、事例とともにご紹介します。
2022.03.22導入10日目で22万円超?物販売上を急激に伸ばす「CBD」接骨院業界でも少しずつ広がりを見せている「CBD」。物販として導入し、初回の仕入れ分が10日間で全て売り切れた…という接骨院からの声が挙がっています。月間最高売上が140万円を超える院もあるほどです。接骨院でなぜここまでCBDの売上が伸びるのか、事例とともにご紹介します。 -
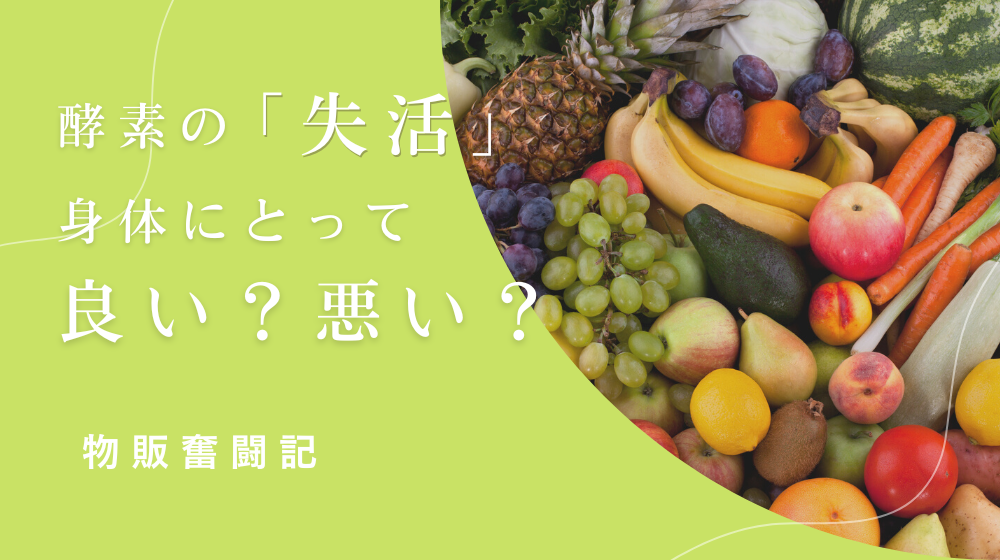 2022.10.27酵素の「失活」は 身体にとって良い?悪い? 【物販奮闘記】酵素とは。・・・説明することは容易ではありません。ただ言えることは、この文章を書いている僕も、読んでいるあなたも、現在進行形で酵素を消費しているのです。酵素が無ければ、身体は何もできなくなるといっても過言ではありません。今回は「酵素」のお話です。
2022.10.27酵素の「失活」は 身体にとって良い?悪い? 【物販奮闘記】酵素とは。・・・説明することは容易ではありません。ただ言えることは、この文章を書いている僕も、読んでいるあなたも、現在進行形で酵素を消費しているのです。酵素が無ければ、身体は何もできなくなるといっても過言ではありません。今回は「酵素」のお話です。

-
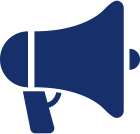 法令など業界の
法令など業界の最新情報をGet! -
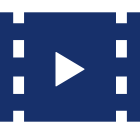 オリジナル動画が
オリジナル動画が
見放題 -
 実務に役立つ資料を
実務に役立つ資料を
ダウンロード

