受領委任制度とはりきゅう療養費
2019年1月より、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
2019年1月より、受領委任制度スタート
2019年1月より、受領委任制度が始動しました。
受領委任制度とは、施術者が患者から一部負担金を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成・保険者へ提出し、受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取るしくみです。 このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われていましたが、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されました。
ここで、はりきゅうの施術に係る療養費の基本をお話したいと思います。柔道整復の受領委任制度とは少し異なるはりきゅうの受領委任制度を知っておくと、今後の備えにもなるかもしれません。
受領委任と鍼灸療養費
はりきゅう療養費の支給対象から見ていきたいと思います。
・神経痛
・腰痛症
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・頚椎捻挫後遺症
・その他疼痛を主症とする慢性病
はりきゅうの療養費支給申請には、保険医の同意書または診断書が必要となります。
では、そもそも「同意書」とは何でしょうか?
はりきゅう療養費の支給対象は、疼痛を主症とする慢性病であり、かつ保険医による適当な治療手段がないものとされています。そのため、保険医による適当な施術手段がないということを保険医自身が示す必要があります。同意書はそのための意思表示といえるでしょう。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任制度は、柔道整復の場合と大きく異なる点があります。それは、受領委任に参加するかどうかは保険者ごとで個別に決めるということです。
保険者が受領委任に参加しないと決めた場合、償還払いや委任払いなど、その保険者がこれまで行っていた取扱いを継続する形になります。
厚生労働省の発表によると、2019年1月1日時点で受領委任に参加する保険者は全国健康保険協会で48団体(協会けんぽの全て)あります。健康保険組合では25団体、国民健康保険組合で76団体、後期高齢者医療広域連合で17団体です。
今後一定数までは、受領委任に参加する保険者が増え続けることになるでしょう。
受領委任の導入に先立ち、保険医の再同意について口頭同意等が認められなくなり、必ず書面を発行していただくよう運用の変更があったり、再同意の期限が3か月から6か月に変更されたりと、仕組みは少しずつ変わってきています。
正しい療養費の取扱いは、患者さまへの適切な施術提供を可能にします。はり師、きゅう師の資格所有者はいるものの、自費施術でしか提供できていない方は、制度の変化を機に、院内の仕組みも見直してみると良いかもしれません。
登録すると続きをお読みいただけます。
既に会員登録をお済ませいただいている方は、
ログインページよりログインしてお進みくださいませ。
注目の記事
-
 就職活動のススメ【アトリクblog】
就職活動のススメ【アトリクblog】 -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム -
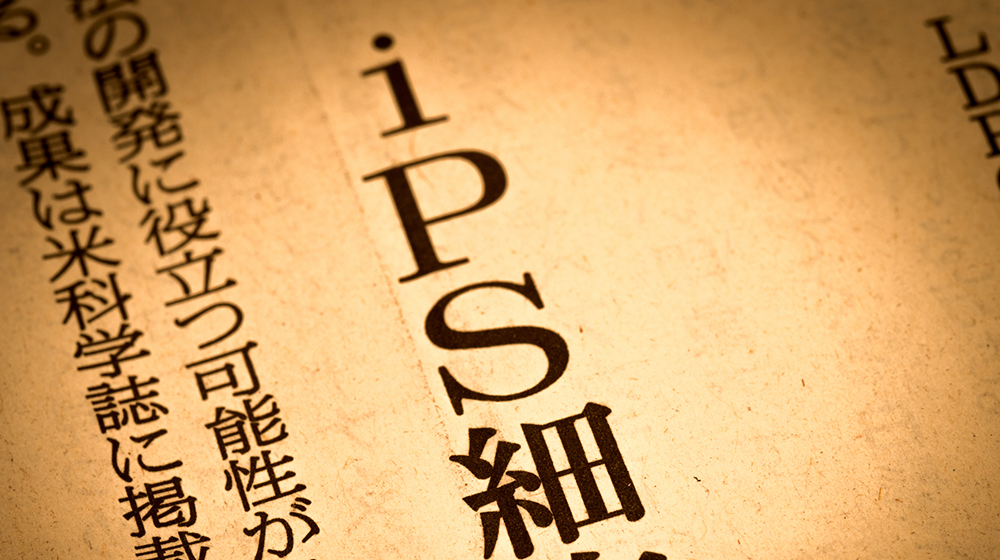 最先端医療連携
最先端医療連携 -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム -
 アトラアカデミー厳選コラム
アトラアカデミー厳選コラム
関連記事
-
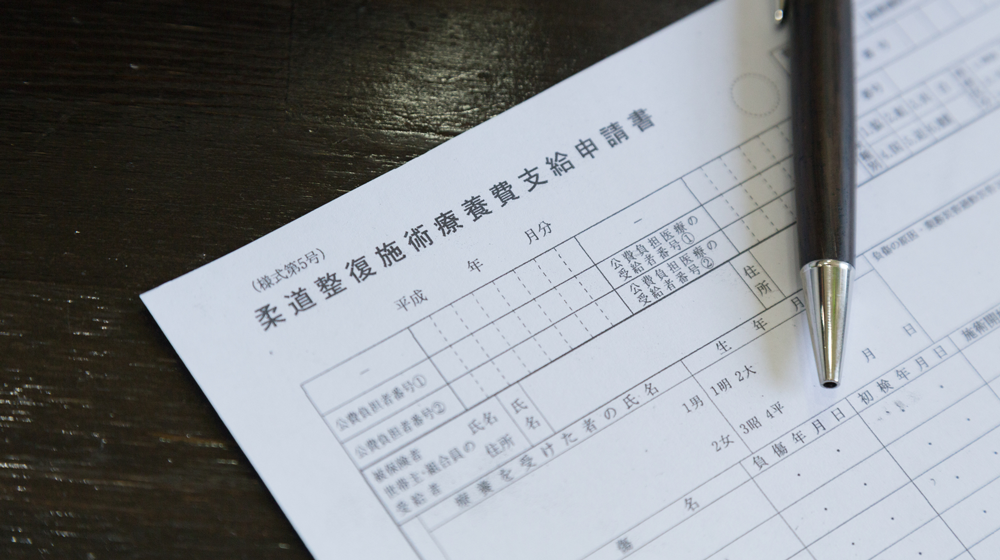 正しい療養費請求
正しい療養費請求 -
 正しい療養費請求
正しい療養費請求
開催中のセミナー
-
 2026.3.7
2026.3.7
関連記事
-
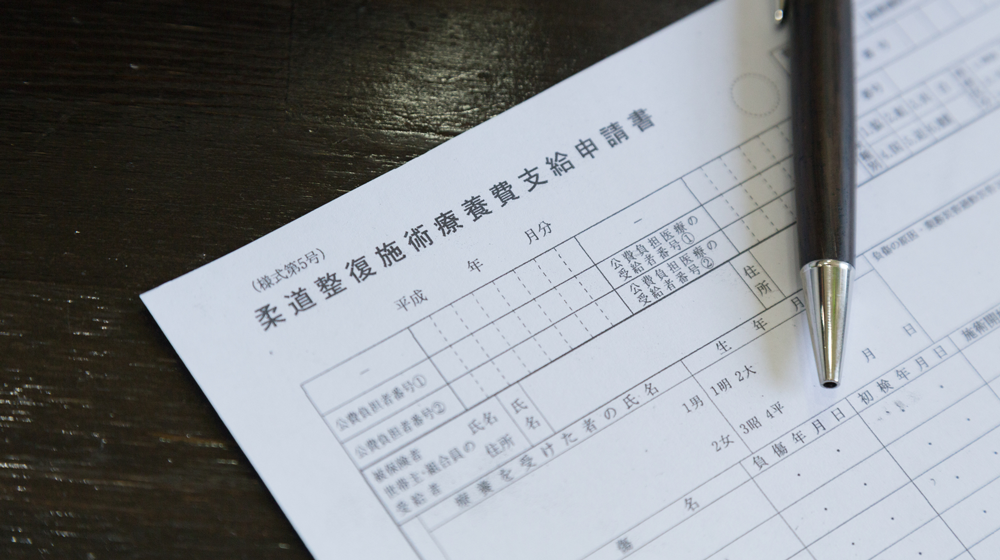 2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。
2021.07.16柔道整復の療養費制度~償還払いと受領委任~多くの接骨院で取り扱われている受領委任制度ですが、受領委任の理解度については少し不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。原則、療養費は償還払いであるのに接骨院で受領委任が適用されるのはなぜか、受領委任のメリット・デメリットは何か。今回は、療養費制度の要である受領委任について詳しくわかりやすく解説します。 -
 2023.03.09交通事故患者への対応方法~施術中・施術後~前回の【交通事故患者への対応方法~施術前~】に引き続き、今回は【施術中・施術後】に行う、交通事故患者への基本的な対応方法・注意点を解説します。(公開:2019年12月27日、更新:2023年3月9日)
2023.03.09交通事故患者への対応方法~施術中・施術後~前回の【交通事故患者への対応方法~施術前~】に引き続き、今回は【施術中・施術後】に行う、交通事故患者への基本的な対応方法・注意点を解説します。(公開:2019年12月27日、更新:2023年3月9日) -
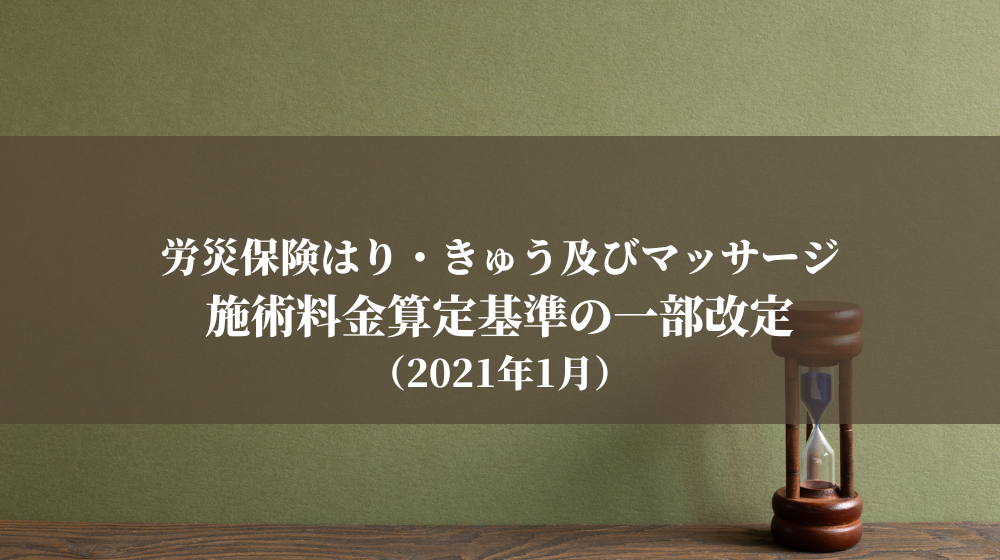 2021.01.25労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。
2021.01.25労災保険はり・きゅう及びマッサージ施術料金算定基準の一部改定(2021年1月)厚生労働省より、2021年1月18日付で労災保険における「はり・きゅう及びマッサージ」の施術について、料金算定基準の一部改定についての発表がありました。令和3年2月1日以降の施術分について適用されます。

-
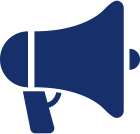 法令など業界の
法令など業界の最新情報をGet! -
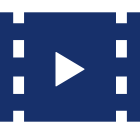 オリジナル動画が
オリジナル動画が
見放題 -
 実務に役立つ資料を
実務に役立つ資料を
ダウンロード

